粘土やZbrushなどで粘土造形が上達していく練習方法の過程で外せない要素。
それは実際の存在している(いた)生き物の形をトレースして学ぶという「リアル」というジャンルです。
粘土造形が上達する上でどういった要素が必要か分解して考えていくと次の3つに大きく分かれると思っています。
◉狙った通りの動きが出来る
◉リアルな形が分かっている
◉ファンタジー(演出的)な形を使いこなす
それでは解説です。
まず、
粘土造形における狙った通りの動きとは、
自分が狙って掘ったら思った形に掘り込みが出来たり、
狙って盛り付けた時にその粘土の量や想像している形に出来ることを言います。
その他、モノの傾きや正中が取れるようになったりとこのあたりも大事な部分になります。
サッカーや野球でも狙ったところに蹴ったり、投げたりを練習するのと同じように、
粘土造形でも掘ったり盛ったりを繰り返して感覚を鍛えることで徐々にレベルを上げていくことが出来ます。
この部分は誰しもが出来る部分であり、練習量が全てであると言えます。
そういえば、武井壮さんは思っている通りに体を動かすトレーニングを毎日行っているそうですが、
まさにそれと同じことですね。
造形は手先だけなので比較すると大分楽な気がしますね。
次に、
リアルな形とは
こちらは過去記事でもよく書いていることなのですが、
大前提として粘土造形が上手に見えるということの必須条件はリアルな形が入っているかどうかにあります。
人は何がリアルに感じるのかをその人が今までに見てきたものでしか判断が出来ない生き物です。
というより存在していないものは単純にリアルとは言えないですよね。
なのでオリジナルのクリーチャーなどを作る時は必ず実際に存在する生き物の何かをベースにして
デザインをしていかないと成り立たなくなってしまいます。
関連記事
映画で登場するクリーチャーは実際には存在しませんが、
形をデザインする上である程度存在している形=リアルな形を入れ込むことで
説得力のあるリアリティーを感じられるキャラクターを作ることが出来ます。
有名なキャラクターをよくよく見てみるとリアルな形の忍ばせ方が学べます。
3つ目は、
ファンタジーな(演出的な)形を使いこなす。
この要素に関しては簡単なものであると同時に難しいものにもなりえます。
この部分は今回の本題ですが先に基本的なところの説明です。
ファンタジーな形とは演出的に形の稜線の流れをメリハリのあるダイナミックな流れに誇張したりすることです。
ファンタジーな形はかなりセンスの必要な技になってきます。
このダイナミックな誇張は漫画やイラスト、カリカチュア等がわかりやすいと思います。
私は幼少期から漫画を真似て絵を描いていた経験があり、
ファンタジーな形のエッセンスを少ない量ではありますが養えていました。
このファンタジーの形を使いこなす点での注意は、
リアルの形が土台にある上でファンタジーが生きるということです。
なのでいずれにせよリアルな形の習得は必須になってくるのです。
粘土造形を始めたばかりの頃の私はファンタジーの形を無駄に使い過ぎて形をよく誤魔化して良く見せていました。
これではプロにはすぐバレてしまいます、
当時、SFXキャクター造形師の片桐さんに見て頂いた時には速攻で叩きのめされました(笑)
特殊造形界では20歳でプレデターを作り上げた Steve Wang氏、
第一線で活躍中の造形アーティスト AKIHITOさん、このお二人は
特にファンタジーな形を使いこなす達人だと思います。
毎回新作が出る度に沢山のエッセンスを頂いております。
ちなみに私の中で片桐さんはリアルとファンタジーをバランス良く共存させる達人というポジションのお方です。
つい最近知った言葉なのですが、「外連味」(けれんみ)という言葉、皆さん知っていますでしょうか?
意味は、はったりを利かせたりごまかしたりするようなこと。
ファンタジーの形はまさにこの外連味のことで、
実際にはもっとプラスになるイメージで活用します。
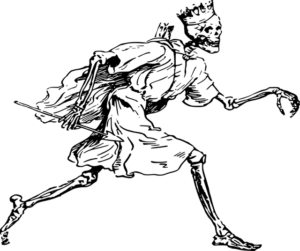
ではここからが今回の本題となります。
リアルの追求による弊害もある
粘土造形を上達させていく上ではリアルの形は必ず学んでいくのですが、
学べば学ぶほど造形の形がこじんまりして迫力に欠けるようになっていく時期が来ます。
ある程度のリアルの形は正解が分かりやすく、楽しく、そして形を良く魅せる単純な方法なので全ての形に取り入れたくなってしまいます。
その結果、とにかくリアルな形が大事という縛りが自然に身に付いてしまうのです。
私は特にここにハマってしまいまして、、、まだ渦中にいます(笑
もちろんこの障壁は作る目的のものにもよるのですが。
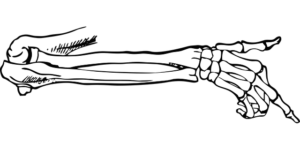
リアルの形とは実際にあるものなので、人は当たり前のようにリアルを認識しています。
この意識をしていない認識というものが造形にとって厄介者で、
造形知識の無い方が見た場合でもリアルかそうでないかの判断が簡単に出来てしまいます。
下手な造形という言葉通り、玄人にも素人にも判断が簡単です。
逆に上手な造形では素人にとってはある程度のレベル以上になると同じクオリティーに感じることがあります。
なので下手な時期こそリアルの形を取り入れるのは先決になります。
リアルな形がどの程度身に付いたかの判断はとても曖昧ではありますが、
それと同時に外連味を活かす技術も忘れてはいけません。
人が当たり前のように無意識に認識しているリアルな形。
この認識外を提案していくのがファンタジーの形になります。
スーパーリアルな造形を作る場合にはファンタジーはあまり必要ありませんが、
そうでない場合は多少なりともファンタジーの形を入れ込むことでそのキャラクターが強調されて良い方向に魅せることが出来ます。
このファンタジーの形を説明することはなかなか難しく、
さらに言葉でとなるとまだ言語化されていない領域です。
ファンタジーの形を学ぶにはやはり先駆者の良い造形からそのエッセンスを真似ていくのが一番の方法です。
今後このあたりを言語化して記事に出来ていけたらなと思っています。
人によってはリアルの形を追求し過ぎないほうが良い場合もある?
私は特殊造形の世界で生きていますので全ての造形界のことはわからない部分もありますが、
ファンタジーの形は造形レベルの高い人だけが出来るものではなく、
その上達の途中段階の未熟な部分があることによって生まれる良い形というものがあると思っています。
これはいわゆる「個性」というもので、
リアルな形という縛りを覚えてしまうと無意識化ではこの個性が無くなってしまうことがあります。
ファンタジーの形というものは実際には存在しない形も含みますので、
未熟な時期であるほど存在しない形を作ってしまうことが多いです。
その存在しない形の中で稀に世間との相性が合致して個性に変化する場合があります。
個性というものは、偏愛的な要素なので万人に受けるものではないです。
逆にリアリティは万人に受ける要素であり、ロジカルな要素だとも言えます。
何事でもそうだと思いますが、
全てを合理的にロジカルに行き過ぎると何か大切なものを見落としている気がする時ありますよね、
この個性もまさに感情の部分でもありますので、
個性も大事な要素になります。
アートトイやソフビのような可愛らしい形の造形もまさに個性的で、
人はこの造形技術を買っているというより、感情が刺激されて好きになっているという感じです。
なので現時点での自分の個性が世間と相性が合っている場合には、
単純に形の上達をせず、個性の領域を展開していく方が好転していくのではないかと思います。
私のいる業界ではリアリティーは必ず必要な技術なので
この個性との向き合い方をいつも考えさせられます。
私の場合、仕事では個性を抜いて造形をすることが多いので
たまに個性的キャラクターが強いものの制作が来た時にはこのリアリティーの縛りが
無意識に働いて奇抜な形が作れなくなるときがあるのです。
高度なファンタジーの形ではない場合、未熟系のファンタジーを取り入れてしまうと
その箇所だけ造形が下手に感じて意識的なブロックが起きてしまうということです。
なのでその制作の度に出来るだけそのキャラクターに必要な情報と方向性を確認して
必要な個性を都度意識的に装備し直して造形に向かっています。
(と言ってもまだまだ無意識になってしまう時もありますが・・・)
リアルとファンタジーの配分
たまたまその個性が良いものとなればそれは本当に幸運なことですよね。
人の数だけ少なからず個性はありますが、
人によっては個性よりリアリティーを追求することが向いている場合もあることも確かです。
私の場合、どちらかというとリアリティーの方に寄っていると思います。
ただリアルだけでは物足りなさを感じてしまっているので、
自分の中にある個性と共存出来るものを成立させたいと日々悶々と考えています。
リアル 8 : ファンタジー 2 のような。
自分の感情にぴったりハマるリアルとファンタジーのバランスの取れた配分の造形が出来た時には、
それは本当に造形士にとって幸せと呼べる瞬間なのかもしれません。
一番の理想は自分の個性をしっかりと認識していて、
狙った箇所に狙った配分で個性を追加出来ればもう達人の領域です。
私も現在では、リアルな形の中で部分的にあえてファンタジーな形に崩しては様子を見て
試行錯誤しながら正解の形の量を貯めている段階です。
皆さんはこの問題、如何でしょうか?
リアル系の造形が続き過ぎると本当に麻痺してきますので注意が必要です。
何事も中間位置に意識を戻しておくことが大事ですね。
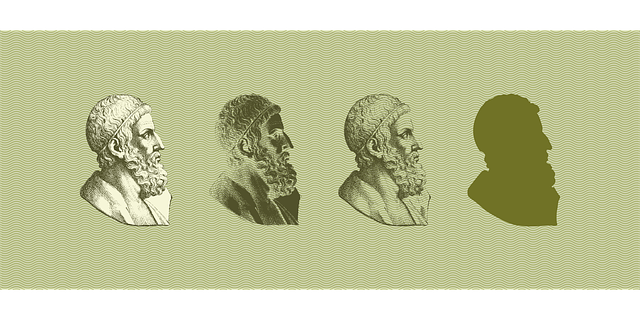
それでは、良い造形ライフを! ーGoushiー
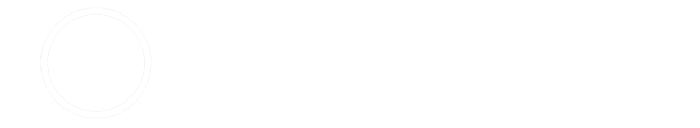
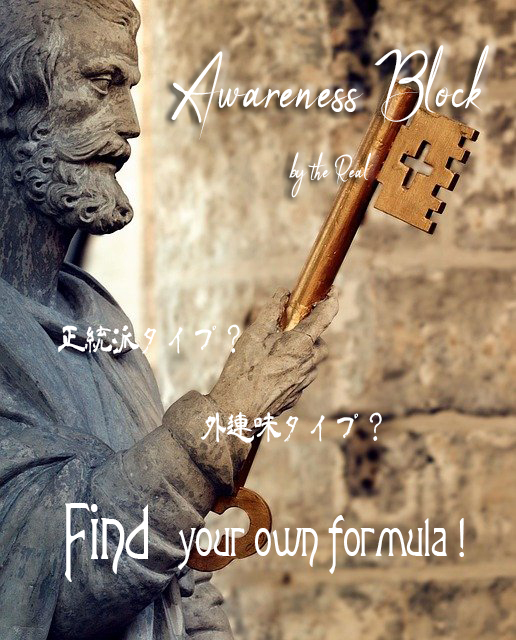

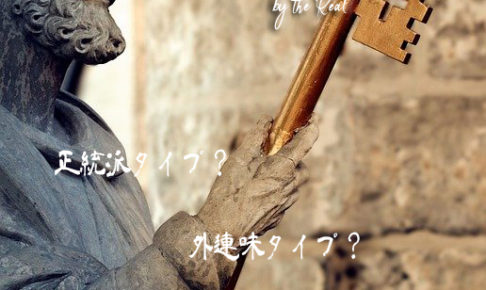











コメントを残す